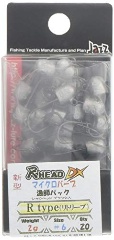難攻不落のクルクルバチパターン!攻略法と意外なオススメルアー
作成:2019.09.03更新:2021.09.04

目次
難攻不落のクルクルバチパターンとは?
シーバスフィッシングにおける最難関パターンの1つでもあるクルクルバチパターン。時合いになると一斉に水面を覆い尽くすほどのクルクルバチが出没、同時にそこら中でシーバスのボイルが始まり、何が何だかわからずあたふたしている間にあっさり時合い終了...と神出鬼没でつかみどころのないイメージを持っている人も多いのではないでしょうか?
また、実際にクルクルバチのバチ抜けに遭遇したことはあってもあまり認識がない人も多く、「ああそういえばなんか動きの速いバチいるよね。あれがクルクルバチ?」と他のバチとの違いをあまりよくわかっていない人も多く感じます。とはいえ、そもそもボイルしている魚数が多いことが多く、適当にルアーを投げてもそこそこ釣れることから、全く釣れないパターンというイメージを持っている人は少ない印象です。しかし、他のベイトパターンに比べてボイルの数とバイトの数が圧倒的に釣り合わず、「あんなにボイルしているのに全然食わない...」と悔しい思いをすることが多いのは事実です。
クルクルバチ(トリックバチ)とは
一口にバチと言ってもいろんな種類のバチがいますよね。どの種類も、見た目やバチ抜けするタイミング、泳ぎ方もかなり異なりますが、そんな中でもクルクルバチ(トリックバチ)とはいったいどんなバチのことを言うのでしょうか?

クルクルバチとは一般的に、秒速50cmほどのスピードでクルクルと八の字を描くように泳ぐ、1cm~2cmほどのアオイソメやゴカイのことを言います。他のバチは大体もっと長くてもっとゆっくり泳ぐ種類が多い中で、少し変わった存在ですよね。
また、見た目や泳ぐスピードだけでは無く、“時合いの短さ”も大きな特徴の1つとなっています。基本的に大潮周りの日没後の満潮潮止まりがクルクルバチのバチ抜けの時合いとされており、ピーク時は雨が降っているのではないかと勘違いするほどのクルクルバチによる波紋が一面を覆うのですが、潮が下げ始めるとスーッと消えていきます。
ポイントや潮回りによっても変化するのですが、バチ抜けが起こっている時間は長くて2時間ほど、短い場合だと30分前後で終わってしまうこともあり、タイミングを外してしまうと、さっきまでボイル祭りだったポイントでも、何事もなかったかのように静まり返っていることもあります。ちなみにクルクルバチにおけるバチ抜けも、他のバチ同様、産卵のために普段は地中にいるバチが水面付近に出てくることを指します。日没後にバチ抜けする理由も他のバチと同様で、鳥などを避けるためとされています。
ルアーでは再現しにくい素早い動き、1度に大量にバチ抜けする点、時合いの短さ、この3つの要素がクルクルバチパターンが難攻不落であるとされている大きな要因です。
クルクルバチパターンが成立する時期

エリアによっても異なりますが、およそ3月末から7月初旬まで成立します。この辺りは他のバチとも大差はありませんね。強いて違いをあげるなら、他のバチに比べて若干シーズンインが遅く、少し水温が暖かくなってきた頃からが狙い目です。またエリアによっては9月中頃から10月頭にかけてもバチ抜けが発生する時期がありますが、この点も普通のバチとあまり変わらないように感じます。
クルクルバチが抜けるエリア
こちらも基本的には普通のバチとあまり変わらず、主に河川などの泥底エリアを好みます。ただ普通のバチに比べて若干塩分濃度の濃いエリアを好む傾向があり、具体的には運河や港湾部、河川であれば河口付近などがポイントとして適しています。

▲(写真)キャッチしたヒラセイゴ。秋頃、河川などでも塩分濃度の濃いエリアでバチ抜けが起こると、ヒラセイゴが食ってくることが多いです。
トリックバチやトリッキーバチとよばれることも
今回は“クルクルバチ”として解説していますが、筆者の住んでいた和歌山県では“速バチ”などと言われることも多く、これは関西地方でのクルクルバチの別称です。そのほかにも関東地方では“コバチ”と言う人も多いそうです。他には“トリックバチ”、“トリッキーバチ”なんて言う呼び方もネットで見たことがあります。有名なアングラーの発信や、雑誌の記事などによってもまちまちで、統一性がありません。アングラーの間でも、「前の大潮でさ、あの川速バチがいっぱい抜けて、よう食わせんかったわ〜」、「え?速バチって、クルクルバチのこと?」みたいなことがよくあります。とにかく呼び方はいろいろありますが、全部同じクルクルバチと考えてOKです。
引き波を立てるバチなど他との違いは?狙い分けは?
クルクルバチパターンが最盛期を迎える同じ時期、その他のたくさんのバチも最盛期を迎えており、釣りをしているとクルクルバチに混ざっていろんなバチの姿を見ることができます。例えば10cm前後のウネウネゆっくり引き波を立てて泳ぐバチ、5cm前後でかなり細身なバチ、中には30cm近くある種類もおり、どれもシーバスからすれば格好のベイトになっています。
釣りをするアングラー側からすると、アプローチの仕方などが変わってしまうので、少しややこしい話ですよね。とはいえ基本的にシーバスはその場で最も多くて簡単に食べることができるベイトを捕食する傾向があるので、クルクルバチが出ているピークの時間はほぼ間違いなくクルクルバチを狙って捕食していると考えて問題ありません。なにせかなり大量にいますから、シーバスにとっては回転寿司30分食べ放題!みたいな感じかなと思われます。
また、よくあるのが、クルクルバチが沈んでからは普通の長いバチ食いになるパターンです。クルクルバチに比べて、他のバチは時合いがかなり長いので、多くのシーバスは徐々に普通のバチ食いにシフトしていきます。ハク(ボラの幼魚)なども多くなってくる時期ですが、どんな種類でもバチが抜けていれば、バチ食いと判断して問題ありません。しっかりと普通のバチ用のルアーも準備しておきましょう。
クルクルバチ食いシーバスの攻略法

▲(写真)クルクルバチパターンにおけるアベレージサイズのシーバス
冒頭でも触れた通り、シーバスフィッシングにおける難攻不落パターンの1つであるクルクルバチパターン。一面を泳ぎ回るクルクルバチに、規則性無くあちこちで頻発するシーバスのボイル、どんなルアーでもどこに投げても釣れそうですが、ことごとく無視されます。とはいえそれっぽいルアーを適当に投げていればポロっと釣れることも多く、もう全く釣れません!お手上げです!なんてことはあまりありません。
なので、「よくわからなかったけど、今日はボウズじゃなかったしまあいっか」となりがちなのですが、それでは安定した釣果をあげられません。時合いが短いので焦ってしまいがちですが、落ち着いてよく見るとシーバスのボイルにも変化があることに気づきます。何か規則性を見つけられれば、バイトを増やす方法を考えることが可能です。
シーバスは極力楽に捕食したい(特に大型は)
一面で縦横無尽に起こるシーバスのボイルですが、よく見ると規則性があって、明らかにボイルが多い場所、少ない場所があるのに気づくことができます。またボイルの出方も派手に水柱を立てるものから、静かに吸い込むだけのものなど違いがあります。これらの違いから、何が推測できるでしょうか。

▲(写真)クルクルバチを口いっぱいに捕食した大型シーバス
特に大型個体に見られる傾向ですが、基本的にあまり動かず、楽して捕食している傾向にあります。特にクルクルバチは1匹あたりのカロリー数も少ないので、より消費カロリーを抑えつつたくさん捕食する必要が出てきます。したがって、あちこちでクルクルバチが泳いでいる状況で、バシュッ!と派手に水柱をあげながら捕食して回っているのは基本的に50cm以下である場合が多いです。大型個体は地形や流れの影響で、クルクルバチが流れ込んでくるようなポイントを陣取って、クルクルバチが流れてくるのを待っていることがほとんどです。基本的に小型に比べて動きもゆっくりなので、捕食の仕方も非常に大人しいことが多いです。水面に落ちた羽虫を食べるトラウトのようなイメージですね。
クルクルバチが流れてくるポイント
待っているだけでクルクルバチが流れてくるポイント、なおかつシーバス自身が自分の安全を確保できるポイントであれば、高確率で大型がついています。サイズはそのポイントによって変わりますが、そのエリアで1番条件の揃ったポイントにはそのエリアで1番大型のシーバスがついているイメージです。例えばここぞ!と言うポイントで70cmのシーバスが釣れれば、その個体がそのポイントでの最大クラスである場合が多いです。
では、具体的にどういったポイントが大型に好まれるんでしょうか。待っているだけでクルクルバチが流れてきて、自分の身も隠せる場所です。橋で出来た明暗部の流心付近はどこにでもあって、条件を揃えていますね。他にも河川や運河の合流点などもオススメのポイントです。流れの変化を見極めにくい場合は、ボイルから推測すればOKです。大人しいボイルが連続して起こっているポイントは、クルクルバチが流れてくると考えて問題ありません。特にバチ抜けが収まってからもボイルが起こっている場所は、弱ったクルクルバチが流されてくるポイントである可能性が高いです。
オススメの最強ルアーと攻略法
まず、普通のバチはボトムだけで抜けていることも多いのに反し、クルクルバチはボトムだけで抜けていることはあまりありません。若干レンジが下がることもありますが、水面付近での釣りがほとんどになります。攻め方は他のバチパターンとあまり変わらず、ボイルのある付近をシンキングペンシルなどのルアーで流れに対してアップクロスにキャストして探ってくるのが基本的な攻め方です。とはいえクルクルバチは一般的なバチに比べて5分の1ほどのサイズですし、泳ぎ方やスピードも異なります。攻め方もルアーが完全に同じと言うわけにはいきません。
約2cmのワームを用いたジグヘッドリグが最強ルアー?
“マッチ・ザ・ベイト”。ルアーフィッシングの基本中の基本ですが、シーバス用のルアーでクルクルバチに合った2cm前後のルアーなんてありませんよね。そこでメバルやアジングなどに用いる2cmぐらいのワームを用いたジグヘッドリグがオススメです。ジグヘッドも1g前後と比較的軽いものを用いれば、水面付近をゆっくりトレースすることができますし、何より1,500円~2,000円ほどと高額な商品が多いシーバスルアーに比べ、コスパが抜群です。
また、針が固定されているために障害物をタイトに攻めた際に根掛かりが少なく、フックアップしたシーバスがバレにくいという利点もあります。ちなみにメバル用のジグヘッドで釣りをする際は尺メバルタックルで釣りをするのがベストです。軽いルアーの飛距離も伸びますし、針が伸びてバレることも少なくなります。
シーバスが相手なので、ジグヘッドは太軸が必須です。
ソフトルアーはピンテール系であればなんでもOKです。とはいえ月下美人ワームはミスバイトにもズレにくくオススメです。
もちろんシーバス用ルアーでも釣れます
じゃあ、シーバス用のルアーは大きすぎて釣れないの?と聞かれてしまいそうですが、そんなことはありません。さすがに14cmの強波動系のミノーなどではちょっと厳しいかもしれませんが、7cm~10cm前後のルアーであれば問題なく釣れます。具体的にはシンキングペンシルなどの微波動で水面付近をトレースできるルアーがオススメですが、シルエットやレンジキープ力を重視して、強波動のルアーをアクションしない程度のスピードでリトリーブして使うこともあります。こういったようにジグヘッドを用いた釣りとは違い、あらゆるルアーを使って反応を試せるのがシーバスタックルで釣りをする魅力かと思われます。
本当にいろんなルアーがありますが、参考程度に、クルクルバチにオススメのルアーを紹介しておきます。ちなみに純正のトリプルフックだと針が小さく、掛かりの浅さが原因でバレることも多いのですが、一回り大きいシングルフックに替えることで対策が可能です。強度も高く、針伸びでバレる確率が減るので、ぜひ試してみてください。
クルクルバチの時期はまめにポイントへ通って観察
釣れれば数は出るものの、大型が少なく、また難易度が高いことからもあまり人気のないクルクルバチパターン。このパターンが始まる頃にはイワシやハク(ボラの子供)といった他のベイトパターンも成立しだすので、地方やポイントによってはあまり縁がないかもしれません。
とはいえ港湾部などが主戦場のシーバスアングラーにとって避けることができないパターンですよね。一見神出鬼没で掴み所のないパターンのようにも思えますが、毎日ポイントに立ってよく観察してみると、規則性が見えてきます。難易度が高いだけあって、パターンをつかめば何人かアングラーが並んでいる中で1人勝ちも実現可能なので、しっかりポイントに通って攻略しましょう。